魔術的現代詩④『魔術的芸術』メモ [魔術的現代詩]
ここでは『魔術的芸術』のイントロダクションを要約することで、『魔術的芸術』そのものの概念を把握しようとするものである。
いわば、覚書。
誤字、脱字、解釈などは追々改めるとして、以下に列記したい。
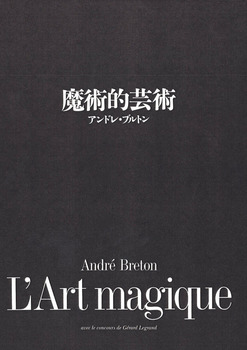
『魔術的芸術』扉
『魔術的芸術』〔普及版〕 アンドレ・ブルトン
監修:巌谷國士
訳:巌谷國士、鈴木雅雄、谷川渥、星野守之
(河出書房新社・2002年6月30日・3,800円)
魔術的芸術の概念
■ノヴァーリスの思想をもとに
・(魔術的芸術は)自ら促進し切望しようとしていた芸術の形態の一つ。(P21)
・パラケルスス「天にあり地にあるもので、人間の中にも存在しないものはない」(P23)
・スェーデンボリ「あらゆる外観、あらゆる物質の形態は、自然の最奥に潜む源泉を見透かせている仮面、包皮であるにすぎない。」(P23)
・上の二つをわがものとし、「われわれは宇宙のあらゆる部分とばかりでなく、未来、過去ともつながりを持っている。とくに重要であり有効であるように思われるこうした強力な関係を確証できるかどうかは、われわれの注意の方向と持続力しだいである。」(P23)
・「世界がわれわれの意思に合致するかどうかどうかは、われわれ自身にかかっているのだ。」(P23)
・「魅力的な娘というものは、人が思う以上に本物の魔法使いである。……すべての精神的な接触は、魔法の杖との接触にている」(P23)
・ノヴァーリスの目からすれば、魔術はたとえ儀式用の道具を失っていても、私たちの日々の生活の中で、その効力のすべてを守り続けているものだろう。(P23)
・ノヴァーリスは、魔術的芸術について、覆いかぶせた言葉で自分の考えを表明している。いわく、「数学は法にしか、つまり法的な自然や法的な芸術にしか関与せず、けっして自然や芸術そのものには係わらない。自然や芸術が魔術的なものになるのは、ただ徳化されるかぎりにおいてである。愛こそが魔術を可能にする原理だ。愛こそが魔術的に作用するのだ」と。(P24)
・「特化」(モラリザシオン)=「精神化」、「徳」、つまり精神的なものに強調が置かれているのは、「フィジック(物質的)なもの」が重くのしかかるつらさを取り除くため。(P24)
・「愛」=精神化され、純化された欲望という意味。「愛する心は、精神のあらゆる要望を満足させる。」(P24)
・これが、充分に進化を遂げた魔術的概念である。(P24)
・魔術は「それ自体として一つの意思にほかならず、その意思にこそあらゆる不思議、あらゆる秘密の大奥儀である。それは存在の欲望の求めに応じ作用する。」(ヤーコプ・ベーメ)(P24)
・上記がノヴァーリスの思想の核心であり、哲学的なものと詩的なものとが合一している地点からこそ、魔術的芸術のまったく異なった二つの側面、二つの様相が、はっきりした形で現れてくるだろう。(ブルトン)(P24)
☆この二つの側面を美術史の枠組みの中でブルトンらが考察するもの。
一方は、必ずしも魔術の直接的表現ではないが、少なくともそれと密接な関係をもっている芸術。→時間と場所に応じて変化しながらも、一つの明確に規定されているある種のコードに従い、現に実践されているような魔術。→人類の揺籃期に形成基盤が見出される。
もう一方は、魔術の組成がすべて消え去ったあとにも生き延びるような芸術であって、故意にであろうとなかろうと、(意識的であると否とを問わず)その後もやはり魔術の手段のいくつかを活用しなおすもの。→これらに見られる魅力によって、目の届く限りの未来を誘い込むもの。
日常の用語方として「魔術的芸術」といった場合、上記の二つのものが混同して、厳格さを欠きながら存在している。(P24~25)
■魔術と宗教の違い
・「魔術」という言葉から――この言葉は、多かれ少なかれ非合理的な性格をもった秘密裏の実践を拠り所にしつつ、自然の諸力を傲然と支配することを目的とするような、人間のさまざまな行為の全体をつつみこんでいる。(P26)
・魔術の特殊な性格の一つ→「あくまでも拘束する」ということ。これが、宗教と根本的に区別される。
・魔術は服従を命じており、違反すれば多くの場合制裁される。(P26)
・「魔術の儀式性は、典礼の各細部に明示されている一つの強い意志の表現であり、その意思は、通常の場合、人間の影響をまぬかれている自然の諸力の支配を求めるものである。」(J・マックスウェル博士)(P26)
・反対に宗教は、「超越的な諸力の贖罪あるいは和解」を目指している。(フレイザー)(P27)
・「供物」は、魔術にも宗教にも共通のもの。(P27)
・「魔術」は抗議、反抗を前提とし、傲慢である。→人間がことをなすことを認める、命令に逆らったものには罰する権利まで与えている。(P27)
・「宗教」は、諦念を前提としている。人間はそこに悲哀と自らに課する苦行以外の何物も期待しない。謙虚である。→というのは、人間をそそのかし自分の不幸についてまで感謝させる。しかも、自分の願いをかなえることを拒否した全能者に対して。(P27)←※ブルトンの宗教嫌いが感じられる。
・上記二つは明らかな違いであるが、「だが、魔術と宗教それぞれの起源を対置しようとするとき(発展過程の比較研究や、時代の流れの解釈の問題を設定するとき、さまざまな困難と論理が対立しあい、例外が多く激しくぶつかり合う。(P27)
・社会学者たちと民族学者たちとは、客観的な配慮を注いでいるだろうが、根本的に相容れない立場の擁護者である以上、自分に有利な論拠ばかりを採集しようとする。
そういう時、隠秘学者たちにも発現の権利がある。――魔術は彼らにとっては死語ではないという権利。しかし、隠秘学者もあらかじめ構想された世界の体系から出発しているわけで、社会学者や民族学者たちとの交流する機会を奪われている。(P28)
・「魔術は世界の調和のもとづくものであり、共感によってたがいに結ばれた種々の力を用いて働く」(ロベール・アマドゥー『隠秘学』)(P28)
■アニミズムの原理
・「人間の中には<原型的存在>の一要素、一植物、一尺度、一理性と照応しないような部分は何一つない」(パラケルスス『魔術』)(P28)
・「魂は、必然的に回帰して、物質と同じだけ個別の魂に分かれる。――物質の中には、魔術から見るとmore magico、個々の体系が他のあらゆる体系の忠実な反映になっていることを妨げるようなことは何もない。(J-A・ロニー)(P28)←この概念は、すでにノヴァーリスのよって共有されていた。
・すでに18世紀にしてアミニズムの原理がヒュームの手に取り上げられている。すなわち「人間性の内には、あらゆる存在が人間と似ているように思い、人間にとって親しい全ての性質、人間が内面で意識するすべての性質を対象に付与しようとする。そんな普遍的な傾向が存在している」(『宗教の博物誌』)(P28)
・「魔術はアニミズムの技術のもっとも原始的で最も重要な部分を構成していり……魔術は、自然の精神化が完遂されていないような場合、どうやらまだ応用される機会がある」(フロイト『トーテムとタブー』)(P29)
・原初の人間たちは、観念の秩序を自然の秩序ととりちがえており、観念を制御できる以上、同じように事物を制御することが可能だと想像していた。ある「共感の法則こそが、自然と人間の関係を、人間に有利なやり方で調整できる。(J-G・フレイザー、タイラー)
種々の観念の連合を類似に基づいて(模倣魔術)、時には空間と時間における隣接のもとづいて(感染魔術)支配すことに他ならない。(P30)
・魔術の根本母体=「マナ」の概念は、魔術と宗教の根株をなす問題(フランスの社会学派もイギリスの民族学者も共通)(P31)
・「煙をたいて雲と雨を呼び起こすという行為に含まれる魔術的な判断は、煙と雲との原初的な区別がまずあって、その両者に結び付けるためにマナに呼び掛ける、ということではなく、思考のより深いところで煙と雲が同一視されている。(レヴィ・ストロース)(P31)
・すべての魔術的行為は、ある合一性の回復に基礎を置いているが、その合一性は失われたものではなく、無意識的なものであるか、行為自体ほど十分に意識されていないものであるかである。(レヴィ・ストロース)(P31)
・「原始人にとって、アニミズムは自然な概念であり、それ自体のうちに正当化の根拠をもっていた。(フロイト)(P32)
・科学界(民族学者、社会学者、宗教史家、精神分析学者)は、魔術を想像的能力の逸脱とは違うとする考え方をひどく不審の目で見ている。そんな精神は、すでに遠い昔にしか居場所がなく、人類の歴史の黎明期がどんなものか検証するためにしか価値がないとしている。(P32)
・しかし、魔術的精神をもつものは、現実の力を意のままに用いる活動としての魔術がかつて存在したばかりではなく、今も存在すると主張する。→これが、最大の不評、最悪の避難、狂信者、ペテン師、として対応された。←「論証的認識」がないため。
では、詩や芸術の世界でそんな認識の言いなりになっていたならとうの昔に想像力は消えていただろう。原典解釈では詩の真価は引き出せない、技法分析では芸術作品の真の効力を何一つ引き出せない。(P32)
☆魔術の伝統に人生をささげている人ならだれでも、詩や芸術に人生をささげている他の人々同様、その伝統の内に認められる永続的な現実と、その伝統の内にあると信じられる種々の力とに合わせて、自己の全内的存在を形作っているのだから、批判的な目で見るような人々に比べて、魔術については常により多くを知るようになるだろう、ということ。(P33)
・「マナ」と同様、「流体」「元素霊」など、合理的分析を拒む概念を拠り所とせざるを得なかった。(P33)
・しかし、詩人たちや芸術家にしても、自分を高揚せしめ、自分の表現の調子にもっとも重大で異論の余地のない効力を与えるような何かに「名前」を付けるとなると同じだけ困難だということ。これは「霊感」という言葉も同じである。(P34)
・論証的認識⇔叙情的認識で、これは言葉の力の再認識に基づいている。
・詩人や芸術家と、魔術的行為の有効性を主張する人々との共通する意見は、「言葉」に与えているところの、高度な、伝達しにくい意味内容の上にある。(P34)
・「ある農夫が毎朝同じ時間に起きて、陽ののぼる前に家からずっと遠いところへ行き、同じ草を毎日1本ずつ摘むことをしたとすれば、彼はこの草を身につけることによって、数多くの奇跡を起こすことが可能であろう」(『高等魔術の教義と儀礼』エリファス・レヴィ)と証言している。これには、どんな本物の詩人も本物の芸術家も異を唱えない。←これは、公認の教育が、気にも留めないような意見である。(P34)
・エリファス・レヴィに共感する詩人=ビクトル・ユゴー、ボードレール、ランボー、ヴィリエド・リラダン、マラルメ。(P35)
☆現在の意識水準(以前と比べ高いとされている)を超えることの原理一切が、自然の秘密についての学という意味での「魔術」の中にあり、それ以外のところにはあり得ない。←そしてここでの「魔術」は超越的な魔術であり、「妖術」とは違う。(P37)
☆「魔術」:ひとつの教義しかなく、見えるものは見えない物の顕現である。感じ取られ目に見える事柄の中には、感覚にはとらわれず目に見えない事柄と正確に比例する形で完全な「言葉」が存在する。(エリファス・レヴィ)←これは、「合理的思考方式」にとっては、まったく無視するしかない称揚し、まつりあげようとするもの。(P37)
・白魔術(降神術)と黒魔術(降魔術)を区別するのは恣意的であって不正確だ。これは魔術的技巧の目的別に考えられたもので、その本性には基づいていない。魔術は一つしかない。秘儀を授かったものは、これを全のためにも悪のためにも利用する。(ルイ・ショショー『魔術とその教義の歴史』)←ブルトンもこの思想に賛同している。(P37)
■ルイ・ショショー『魔術とその教義の歴史』の概要(P37~39)※これは、主に占星術の概念を示している。
・宇宙は一つの球体の中に包み込まれていて、それは有限でも無限であってもいいのだが、一つの星を中心として重力、磁力、熱力などの基本的力によって、めぐりめぐっている。
・それぞれの衛星、惑星上では、さまざまな存在が組織と構造を与えられており、その作用は恒星に起源をもつダイナミズムである。
・存在はそれぞれの種族の可能性に応じて、だが、常に一つの感応力に従って生きている。主動的恒星に由来するこの感応力こそ、存在を化学的にも生物学的にもこの星と一体化させているのだ。
・よって、動物、植物、鉱物といった被造物がどれほど違っていても、摂理に基づいた調和の具現する一連の関係、それぞれの間に連帯を打ち立てている。
・魔術の一般理論は、原則としてたいていは地上界において適用されている部門である。→これは「万物照応」(コレスポンダンス)の理論である。地上界ではどんな存在もひとつずつ構成をもっているが、それぞれの構造に特有の性格は、宇宙のエネルギーのさまざまな組み合わせの結果なのだ。
・これは、銅とクマツヅラの茎とハトの羽は、構造上は違っていても、同じ一つのダイナミズムの拠点であることには変わりがない。←このダイナミズムは、鉱物の場合は潜在的だし、動物の場合は流動的、活動的だし、知性的ではあるが、どれも同じである。
・占星術の教えるところでは、このダイナミズムは「金星」からきている。したがって、金星に感応されたすべてのものは、ある共感、ある相乗作用が働いていて、実践面では、この感応下にある一人の人間は、それに対応する護符を身につけることによって、自分に特有の潜在能力を増大させることができる。(たとえばハトと牡牛、銅とカーネリアン石など)
・ボードレールの言う想像力とは、「まさしく無限なるものと類縁をもち、世界の始まりにあたって、アナロジーを造り出し、隠喩を作り出したものなのだ。(P41)ブルトンはこの言葉とルイ・ショーのものと同じであると言っている。
・ボードレールは、酔って広い意味に理解された宗教というものが、「人間精神の最高度のフィクション」であるとする。(P41)
・ボードレールは、フーリエを馬鹿にしていたが、フーリエはあらゆる人間関係を再検討することで、その関係を「情念引力」とした。
「情念引力」は、魔術の論理に垣間見られる普遍的アナロジーの人間における表出に他ならない。(P41~42)←シュルレアリスムの数々の遊びの中にも見られる。(互いの中に)
・ボス・コーディモ・ゴヤ・ゴーガンなどの絵画の解読にも、この「互いのなかに」の方法を利用すれば、いたずらに「カバラ的」であったり「錬金術的」であったりする解釈よりも危険が少ない。つまり、「偏向主義」ではないやり方の一つだ。(P42~43)←ダリの、パラノイアック・クリティックも同じ。
■近代絵画の魔術性
・J-A・ロニーがボードレールやランボーの詩の中にあると指摘しているような「隠喩における魔術的-生物学的性格」は、詩だけではなく、抽象的傾向をもつ近代絵画にも見られる。――ビクトル・ユゴーのインクの斑紋、ギュスターヴ・モローのエスキスなど。(P43)
・魔術師、芸術家、詩人に共通する「原初の力」は、「万物照応の理論」こそが、その戦術的転化として提供する。
・これは「一つのイメージは寓意でもなく、未知の事柄の象徴でもなく、それ自体の象徴なのだ」(ノヴァーリス)。一つのイメージは、絶対的な想像性を帯びながら、無垢の広がりをもつ共鳴音を、あたかも宇宙の他の部分と結び付けるようにして私たちの内に響かせるような芸術。(P44)
■再び魔術と宗教
・ここでは、魔術がさきか宗教が先かを決定づけることは避けよう。どちらに傾くか客観的な証拠もなければ、決定的な議論もないからである。(P44)
・これらの諸説は「一般的な思考の態度に応じて現れたもので、頑固な先入見によっている」すなわち、魔術は最も直接的なアニミズムにもとづいており、宗教ほど入念な仕上げを前提としない以上、宗教に先行するものでしかあり得ない。
一方、あらかじめ原初の啓示への信仰にとらわれている人々にとっては、魔術の儀式は宗教の儀式が退化したか、それとも神聖をけがされたものでしかあり得ない。という二つの考え方がある。(P44)
・とはいえ、魔術と宗教はともに分かちがたく混ざり合ったものであり、その後の絶え間ない両者の相互干渉を考慮に入れなければならない。(P44)
・「あらゆる時代、あらゆる場所で魔術は行われてきたし、こんにちなお、われわれの間でもそれにふける者がいる。一人の学生が寝る前に教科書を枕の下にしのばせる時、彼はいくばくかの魔力に頼っている。(フランソワ・レグザ『古代エジプトにおける魔術』P44~45)
・こうした中で、芸術における魔術的なものと宗教的なものを区別することはひどく難しいだろう。(P45)
・両者の象徴体系は、事実広汎な共通記号のリストによっている。よって、遠く離れた文明であればある程、その解釈は骨が折れる。「二つの宗教体系が両立できなくなると、弱い方の体系は追放され、魔術の性格をもつに至る。」(J・マックスウェル)(P45)←比較的新しい時代であれば、この区別は難しくないように見えるが、今度は宗教が高位聖職者の統制と手を切った瞬間から(離脱行為のことか?)、新しい混同の要素が見えてくる。(P46)
・俗人の見解とは別に、魔術と宗教は何ら敵対しあうものではないのだ。←この場合の魔術は、奥義を極めた人間が「高等科学」の名をあてがっている魔術のこと。
・つまり、魔術師が非の打ちどころのない特性を備えており、その追求する目的が悪とははんたいのものでありさえすれば、カトリック教会も魔術を断罪することは決してなかった。(ルイ・ショショー)(P46)
・ルイ・ショショーは、黒と白の魔術の区別に異を唱えながらも、この区別は魔術を操る時の動機、あるいは非難すべき動機を説明する場合には適当である。←頂上への道は厳しいが、これに向かうための保証は「心の純粋さ」以外あり得ないだろう。(ブルトンらしい結論付け→愛につながる)(P47)
・魔術のデータ、手段や能力をある程度利用している芸術作品を前にしながら、しかも情報がほとんど与えられていない場合、一見して、これほど透明でも不透明でもいないものをあてがわれたと人々は思う。←つまり、それらのもたらす印象に応じてしか、それらの発散するものが有益か不利益かであったりする度合いに応じてしか、その作品を評価することができなくなる。(P47)
・その上、一つの評価の要因がほかの多くの要因と妥協してしまうし、そのいくつかの要因の言いなりになってしまう。(P47)
■魔術的芸術の範囲(概念の確定)
☆魔術の目的に適合しようと決めていようがいまいが、「芸術作品は魔術そのものを起源としている。」ということを忘れてはなるまい。
「あらゆる芸術は、その発生において魔術的であろう」
ということは「魔術的芸術」という言葉は、同義反復ということになる。
この広い意味を避けるとすれば、「芸術を生んだ魔術を何らかの形で自分から生みなおすような芸術だけを、特に「魔術的芸術」として取り上げることだろう。(P49)
・芸術作品は、かつて世界の創造を司ったものと同じ性質のダイナミズムが物質の局面の上に客体化されたものだとする発想が、グノーシス派の人々の間で脚光を浴びている。(P49)
・「肖像画が生きている人間の顔に劣るのと同様に、宇宙は生きているアエオン(永遠なるものの意)に劣っている。とすれば、肖像画を描く動機は一体何か?」と、ヴァレンティヌウスは問うている。←「それは、顔の尊厳である。顔がその名を通して名誉を得るようにとモデルが画家にその顔を提供したのである。つまり、形態がそれ自体見出されていたわけではなく、「名」が作品の原型に欠けていたものを満たしたのである。」(P49)
・聖なる恐怖=「神の名において」造られた自作を前にしたとき(言いかえれば、より高位にある未知の原理を前にしたとき)、芸術家を捉えるのはあの畏怖の念である。←アルニムも同じ発想をしている。(P50)
・アルニムは「未だ創造されていない何者かに対する発明家の信仰(そのために深遠に身を投じ、魂のすべてを混沌にゆだねる信仰)は、優れて神聖なものである。
だからこそ、この信仰は傷つきやすいし、いやしがたい。この恐怖こそが畏怖の念に等しいと。そしてこの宇宙は、われわれの企てに屈することなく、われわれを利用して実験や気晴らしにふけっている。(P50)←プリニウスはアフリカの蜃気楼を、すでにこうした自然の気晴らしのせいだとしている。
☆ロマン派の時代から、今日に至るまで、われわれ自身の力を超える何者かの力にもてあそばれていたり動かされていたりとする感覚は、詩の中でも芸術の中でも、幅を利かすことをやめない。(P50)←「私が考えるというのは間違いです。誰かが私を考えている」(ランボー)
プリニウスは絵画の起源について、「すべてのギリシャ人の言うところでは、絵画は人の影を線でなぞることから生まれた」としている。また、粘土を加工して像を作る方法を発見した最初の人は、娘が男に惚れて、男と別れる時その男の輪郭を線でなぞり、粘土でかたどったことによる」(P53)
・これは、土や鉱物といった絵画を生み出す物質の支えを見失うことなしに、魔術的な角度から考察されている。(P53)
・またプリニウスは、絵画のだまし絵的効果も評価と同時に限界をも示している(鳥とブドウの話)(P53)
・芸術の要求がどんな模倣も受け入れない時、その成功は「偶然」の働き掛けによるものではないか?←犬の涎を描けなかったものが、スポンジを投げつけた時偶然にもそれが再現された。など。(P53)
☆、このように、どんな芸術も魔術と密接な関係を保っていることがよく分かる。しかし、このように魔術に依存しているにもかかわらず、長いこと思考を従属してきた「合理主義」の潮流のおかげで、数世紀にわたって抑圧されてきたことも事実である。(P53)←芸術に豊かさが失われている。
・19世紀を通じて公認のサロンの繁栄とブルジョワ階級の悦楽をもたらした山のような絵画作品は、特にこのような豊かさに欠ける。(P54)
・生活の中でも自然の中でも、月並み調の事物の存在がある。この俗悪で凡庸な存在は、偉大な芸術家たちは忌み嫌っている。とボードレールは言う。(P54)
・またボードレールは次のようにも言っている。
「もしも美を表現することをまかされた人間たちが、教授、審査員諸氏のルールに従うならば、美それ自身が地上から消えてしまうだろう。なぜならば、あらゆる類型、あらゆる感覚が単調で没個性な倦怠や虚無のように果てしもない巨大な統一体の中で混じりあってしまうだろうから」(P54)
・「古典芸術」「バロック芸術」「宗教芸術」にたいして、「魔術的芸術」は揺れの大きいものであり、前記の諸概念と部分的に重なってしまうという事実からもそういえる。(P55)
・美が本当の意味で美しいと感じらとられるためには、私たちの感受性のいくつかのゾーンがそれによって昂り、さらにその高揚を超えて、人間の条件につきものの醜さの感覚から出たこの壁の裂け目を作るのにふさわしい、一連の波動が起こるのでなければならない。←これは、政令によって交付することはできないだろう。(P55)
・ブルトンを含むある種の精神の持ち主には、ある程度魔術的でない美を思い描くことが難しい。これは、美に付け加えられた受動的な、もっぱら反射的な属性であることには変わりない。もはや、美ではない「魔術的なもの」をこそ熱望し、美に対する魔術的なものの優位性を認めることが必要だろう。(P55)
・この行き方は、必然的にアニミズムの段階における歩みを再現することになるだろう。(P55)→つまり、もろもろの存在を統合し、配列し、活性化させている神聖な力を人間に従属させるようなところから始まり、原始的なアナロジーが、初歩的ではない観測を生みだしたその瞬間から、「象徴思考」に達していく歩み方をである。(P56~58)
■古代の魔術的芸術(魔術的トーテミズム)
・古代が残していった作品には、魔術の実践を立証し、しかもある程度それを再構成する助けになるものが数多くある。
しかし、わずかな例外を除いて私たちに働き掛けてきたものは、それらを方向付けた「魔術」ではなく、むしろそれから発する「美」によってである。「美」を副次的にしか追及していない作品の場合でさえそれは同じである。→つまり、そこに暗示されている儀式が長いことヴェールに覆われていたため、別の性質をもった同じ角度の(美的)評価のもとにあったわけだ。←つまり、誤解されて評価されていたということ。(P58)
・これらは、「魔術的芸術」であったにしたところ、肝心かなめの情報量が少なく、それが特別の手ごたえを感じるところまでにはいかないのだ。(P58)
・これと比べて、魔術的荷重を少ししか失っていないものに、各地に散らばって生きている民族集団の活動の所産である。(P58~60)←野性人と呼ぶべきだろう。
・これらは不毛な地域へ追いやられ、狩猟、漁労、牧畜、初歩的な農耕といった資源の少なさから比べると、芸術の旺盛さは心を揺さぶられるほどに豊である。(P60)
・民族学者は、これらの芸術はトーテミズムの内に見られることも一致している。←何よりも魔術的である。(魔術的トーテミズム)(P60)
・ロテュス・ド・パイニは、魔術というただ一つのものだけが、被造物人間に感受することと、思考することと、意志することの三能力を授けてくれたのだと感謝している。(P60)
・そして「大いなるトーテムが古い歴史のすべてを支配していることを知らなければならない」とし、トーテム思想のアボリジニ、ニューギニア、インディアンの芸術は特別のものと位置づけられる。(P61)
■ヘルメス思想
・文明の進歩も、技術の発達も、人間の心のうちから世界の謎を解くという希望を達成することはできなかった。「ひと目ではひどく錯綜しているようにみえながらも、少しずつ解きほぐしてゆくことのできる道筋←ヘルメス思想のさまざまな諸部門。(P61)
・ルネ・ゲノンによれば、「魔術」は下位にあるのだが、諸部門の先導者の役割を果たしている。なぜならば、魔術は幼少期のおとぎ話の生き生きとした登場人物たちを作り出すからだ。(P61)
・魔術の記号のリストは、ヘルメスの諸部門のそれと根本的に同じである。よって、占星術、カバラ、タロット、卜占術、加護祈祷、いくらか保留付きの錬金術を通る図像学的探索を続けていけるはずである。←美しいという角度からはもちろん、これらの作品の価値は実にさまざまである。(素朴なもの、単純なものから最高度の技量に満ちたもの)(P63)
・これら、デューラーの版画も行商文学の木版画との間の尺度の違いはない。両者が私たちに及ぼす魅力は、発揮されている力量とは関係なく、その魅力は突飛な性格に存しており、面喰わせる力の大小に応じている。(P63)
・「美は常に珍奇なもの」(ボードレール)「個性というものを構成し、意義づけ、それなくしては美など存在しなくなるこの珍奇なるものの服用量は、芸術において、料理における風味、あるいは調味料の役目を果たす」(P63)
・幾世紀ものあいだ公認の評価を享受していたかなりの数の芸術作品が、この調味料を根本に欠いているという理由から、価値が低くなっているものもあれば、逆に長いこと好奇心にとどまっていた他の芸術作品が、第一級資料になることもある。(P64)
・そうした作品は、大体が顕在的にであれ、潜在的にであれ、非合理な内容を呈しているものか、かなりの曖昧さを示すものである。(P64)
・ロベール・ルベルは、「ヴァン・エイクからモスタトールにいたるフランドル絵画と、マンテーニャからピエロ・ディ・コージモに至るイタリア絵画は、変身の途方もないリストである」と。(P64)
・同時代人であるボスとダヴィンチ。二重画像はある世界の基礎、正真の造形カバラのカギとなるものだ。←両者はともに統一性に取りつかれていた。ボスは道徳的なものであることを求め、ダヴィンチは、自然なものであると考える。『聖アントニウスの誘惑』など具体例が続く。(P65~68)
・ルネサンスの強要する合理主義的人間主義は、芸術において物理的な視覚に支配権を与え、一切を感覚的経験に関連付けることになる。反動として起こるマニエリスムも、その拘束を狭い範囲で振り払うことしかできない。
それに歴史は、流れに逆らって仕事をする芸術家たちの寄与をできるだけ長い間考慮に入れることを避けている。(P66)
・コージモ、デューラー、グリュネヴァルト、アルトイドルファーといった画家たちの作品が、しばしば謎めいたやり方であるにしても、一つの要請にこたえていた。(P68)
・より身近にあるものではあっても、それらの作品は不信、あるいは忘却に見舞われていたために近づきにくいことに変わりはなかった。そうした作品の典型として、アルチンボルト、カロン、デジデーリオのものをあげよう。確固たる外観を持ちながらも、気まぐれや偏帰志向の産物として見られなかったが、近代の視覚のこうむってきたある種の角度変更を出発点として、別の解釈にゆだねられているように思われる。(P70)
・「謎を呈する」絵画のうち、「歪曲した円錐鏡像」の原理に基づくホルバインの「天使たち」など、まるで媚薬のように働き掛けてくる。(P70)
■プレ・ロマン派
・プレ・ロマン派は、フランス革命、アメリカ独立戦争といった精神的動揺が深い社会的危機に呼応していた時代の表現として、芸術における諸価値の復権を目指す。(P70)
・そのために、これまでの「光明」の三世紀と縁を切り、中世世界のいくつかの強迫観念を生き返らそうとする。(P70)
・よって、19世紀はこの方向に沿って、ユゴーやロマン派の主だった顕楊者たちの造形作品を通して、立場を明らかにし始める。(P70)←実証主義が勝利をおさめた結果、芸術において、見せかけの世界にそむこうとする意志が抑制されるに至る。(P70)
・メリヨンの場合は、誰よりも厳格だったレアリスムの枠組みを破砕せしめ、誰も望まなくなった劇的な別次元の意味を復元するためには、「錯乱」が侵入しなければならなかった。(P70)
・19世紀後半になると、「失われた諸力」を回復しようとする欲求はすでに侵食していたので、詩においても芸術においても、「視覚には、幻視や透視と比べて二義的な位置を与えられた。」←エリファス・レヴィの秘教思想と必然的に再び接するようになる。(P70)
・だからって、「客観的現実性」を自然と競おうとする芸術の信奉者――印象派など――は、武装解除した訳ではない。(P72)
・印象派は光に第一等の役割を与え、ごく小さな気まぐれにさえ頼って光を賛美した。これが、ある一時期、光の新たな正当化を行い、主題の若返りを図った。(P72)
・しかし、印象派と同じ時期に、ギュスターヴ・モローが燦然と輝いてきた。(P72)
・ロマンティシズムの画家C・Dフリードヒの厳命。「おまえの肉体の目を閉じよ、まず精神の目でタブローを見るために。ついで、おまえが、おまえの夜の中に見たものを陽のもとに上らせよ、その作用が、外部から内部へと逆方向に他の存在たちの上まで及ぶように」(P72)
・ギュスターヴ・モローの「神話的象徴主義」から、ゴーガンの「総合的象徴主義」、ルドンの「夢幻的象徴主義」まで、この移行はマラルメやユイスマンスによって保障されることになる。(P73)
・こうした二つの傾向(視覚に頼った印象派――覚醒の時間を捉えて見せた方向と、心の目に頼ったモローなど)は、20世紀にいたって、いよいよ鮮明になり、今日では熾烈極まりない様相を呈している。(P73)
・覚醒の時間に捉えてみた方は(印象派など)その後フランスでは後退し始めている。フォービズムは、ゴーガンやゴッホの教えをその精神において裏切り、視覚神経のみによる知覚からだけ興奮を導こうとする。キュビズムは、純粋な技術上の約束事としてヘルメス的秘儀といって、人間の顔でしかないもを描く。(P73)
■後期印象派とルソー(無意識)
・スーラ以降の後期印象派と、ポン・タヴェン派(フィリジェは例外で)が妥協の道に入り、一方は初歩的な写実主義へと、他方は戒律の厳しい精神主義へと移行しながら、急速な衰退を見せている。(P73)
・それに対して、ルソーが観衆の嘲笑を迎えられながらも、ジャリ、ゴーガン、ピカソ、アポリネール等に興奮を呼び起こしたのは徴候的である。(P73)
・このルソーに対する興味も、はじめは見下したふざけたものだったが、のちには驚嘆へと変貌していく。ルソーをめぐって、はじめて「魔術的レアリズム」を語ることができる。(P72~74)
・私たちの中でも、審美的、合理主義的な先入見のおかげで、それを評価できない状態になっているものと、いないものとの間で成り立つコミュニケーションは、実に突発的で魅惑的なものであり、明らかに大きな効力を発揮し、既知の手段をことごとく挫いてしまうものである以上、「魔術的因果関係」を持ち込むのは当然である。(P74)
・しかし、このルソーの問題が把握されるのは、無意識なるものにあたらしい現実性を授ける見方のおかげでしかなく、その現実性こそが、無意識に対して王者の分け前を与えるのだ。(P75)←この見方は、19世紀からあったものの、20世紀になって初めて照射された。
・「意識とは明確な活動に隠されている潜在能力の孵化であり、転化であり、一つの源泉を有する噴出のこと。無意識は、心理的な、形而上的な、神秘的な性格をまとう。」(P76)
・魅力を発揮できる作品とは、たとえ合理的には正当化できないものでも、意図的にであれ、無意図的にであれ、精神の無意識的領域に根株を下したものに他ならない。(P76)
・ルソーの単純さは、一般には規範からはずれていて、さまざまな禁忌から彼を守っていたが、これをランボーやロートレアモンが全面的な反抗と引き換えに初めて希求しえたものだった。←これは、ゴーガンがもっと素朴に、ポリネシア人のところまで探しに行ったものである。(P76)
■現代作家たち
・フランスでは、ゴーガンのメッセージも、特にフォービズムが視覚神経の昂揚の可能性以外のものをそこから受け止めようとしなくなって以来、台無しになっていたのだが、外国ではムンクがこの教えから全く違う一つの解決策を見出す。(P77)
・ゴッホも、ゴーガンも、人類の運命に対する大きな問いかけの精神が宿っているが、ムンクも、人生の情景を示す悲劇的で狂おしいもの全ての中に私たちを突き落とす。(P77)
・ムンクは、「造形的探索をめぐる内面の動揺を計測するような」ところがある。(P77)
・同じ見方からすると、無限の衝動に基づくものあっても、悲劇性の強度の点でムンクに勝るとも劣らないのがアルフレート・クビーンの作品である。(P77)
・注目するのは、キュビズムの誕生を左右したもろもろの意図、外的対象のすべての側面を同時に伝えようとするキュビズムの意思が、それまで理解されていたイリュージオニスム(錯覚表現)の基礎をなす視覚的レアリズムに対して、一挙に背を向けてしまったという観察である。(P78)
・ピカソの「クラリネットをもつ男」や、ブラックの「ギター弾き」のようなタイプのものは、特定の音楽奏者を画面から消し去り、性質は不明確でも、構造の見分けがつく一つの存在を、私たちの目に生き生きと描き出す。その存在は、自らまとう奇妙な様相によって、よかれあしかれ、私たちをその力に従わせる。←そんなキュビズムの画家たちがどんなに合理的にやろうとも、観者のほとんどが得られた結果しか考えないのが当然で、多かれ少なかれ、同意の上で「鏡の向こう側」にいる自分に気がつくと子になる。(P78)
・ダリは、このピカソの作品を演説するものが誰一人何を描いているかが分かっていないということを思い出して大喜びするが、ダリは、観者の精神の中で、ある本物の革命が行われていたという事実を見ていない。ダリが標榜し続けている写実的など、とうの昔に無効だという事実も見ていない。(P78)
・絵の主題の解明など無視してよい、とまで言わなくても、少なくても副次的なものにすぎないと考えさせることは、言葉の広い意味で、芸術家と観衆との間に生まれる交流は、確かに魔術的であるとみなさなければならない。(P79)
・第一次大戦の前夜に造形芸術の分野で、どんな興奮状態が出現したかは周知のとおりである。(P80)
・1910~1914にかけて、外観だけの世界と手を切って、その代わり何かを打ち立てようとする欲望が前例のない激しさであふれ出ている。文化の新しい欲求と、その要求の感覚的世界におよぶひそやかな反響とに呼応した世界。←その原理は、長い間「模倣」への関心の犠牲になっていたため、「写実主義的」拘束によって、遠ざかれていた。(P80)
・その時代の英雄がアポリネールである。←彼の並はずれた好奇心を満たすことを目的とし、その結果、必然的に彼の深い不安に順応してゆく。この不安があの好奇心と同じ理由から、魔術的な種類のものと確認できる。(P80)
・アポリネールらによって、観衆は、「習慣」に水を差され(現実という幻想から汲まれるすべての安息の喜びを奪われた)、激しく抵抗する。(P80)←観衆には、この幻想が網膜に対するごく特殊な教育の所産であることに認める用意がない。
・「もしも、野性人がわれわれの表現規範に従う一枚の絵を見たとしても、そこに我々の見ているものは何一つ見いだせない。という反論を差し向けられても、せいぜい自分たちの優越性を見出すくらいだ。(P80)
・キュビズムと未来派は、想像しいし示威運動で境界付近に生まれた少数の個人の作品の意図に含まれる、はるかに壊乱的部分を観衆の目から隠してしまう。(P81)
・それらが、一方ではキリコ、シャガール、デュシャンであり、他方ではカンディンスキー、モンドリアンである。(P81)
・キリコは、ソクラテスやニーチェの思想に糧を得ていた彼は、事物の秘密の生命に発するものではないものは、どんな要請も排斥してしまう。(P82)
・物体の外的様相が尊重されているとしても、その物体はそれ自体としてではなく、それを始動させる信号としての関連において愛でられる。←この信号は、運命の感覚、ないし力をもった一本の交線のひかれる可能性が予想される。(P82)
・問題は、すでに形象化された諸要素を一目で識別するささやかの悦びでもないし、「通人」気取りの制作方式を賞味することでもなく、外界の諸相から謎を生じさせるものだけを引き出そうとする絵画は、卜占術と本来の芸術とを一体化させる方向へ向かう。(P83)
・ラウール・アリエの考えるように、「常軌を逸したもの、予想外のもの、不思議なもの、つまり一言でいえば驚きを呼び起こすものだけが、人間の意図に自問を強いることができるのだ。」(P83)
・キリコが、独占的な要請と誘因とを身に受けたこの高位の因果律こそ、魔術的因果律と境を接するものなのである。(P84)
・シャガールは、キリコと同じころ、「感傷的というよりも、むしろ夢幻的な活力を横溢させながら、無尽蔵であると仮定しうる無意識の資源を誇示していた。」(P84)
・シャガールのエロティシズムと、フォルムの透き通る柔軟さは、表現主義とキュビズムに隣り合うものだが、いささかおとしめられている民間魔術の概念をみずみずしくよみがえらすことのできた美質の、典型的な一例である。(P84)
・カンディンスキーは、さらに深い闇な中へ降りていく。「抽象的」という誤解がこれほど行き渡ったことがない。(P84)
・カンディンスキーの壮麗で野蛮な和音は、厳格なあるいは錯乱的な描写と同じく、美的活動のコースをひとめぐりして戻っている。(P85)
・キリコとカンディンスキーを拠り所として、20世紀半ばの「物の数に入る」ほとんどの絵画は発展してきたといってよいだろう。(P86)
・彼ら二人の隠然たる存在は、本物の魔術的な芸術になりすまそうと企てている、紛れものの群れの中にもしばしば感じ取られる。←キリコは、ネオ・アカデミズムに落ちてしまい、夢幻絵画や安物のシュルレアリスムにの先駆になったこと。カンディンスキーは、若い抽象画家によって、悪用されている。(P86)
・実際、そうした画家たちの尊大ぶりと、幾何学の規格大量生産とが、極めて高貴な精神を身につけているはずがない。(P86)
・キリコと、カンディンスキーという天秤の竿になっているのがデュシャンである。デュシャンは、雰囲気の撹乱という方向で作用してきた。(P87)
・そうした作品は、物質的にも精神的にも近づきがたいものであり、反芸術である。(反詩的ではない)(P87)魔術とは「アンチ・リアリティ!」である。(P87)
■まとめ
・今日の批評界は商業界と同じく、思想とも、人生の真の「内的」問題とも何らか変わらない示威行為の数々を大げさにもてはやしている。(P88)
・19世紀を通じて、芸術家と詩人たち、詩人たちと哲学者たち確立されたかに見える合意も、徐々に崩れ落ち、豊かな協議を大きく犠牲にしている。(P88)
・「美」はこれこれの顔をもつようにと催促され、結局は最大多数の理想にあった顔、つまり凡庸な顔をさらすことになる。←真価の混乱、反射行動の抑圧、反詩的な教育がこれほどまで進行したためしはかつてない。(P88)
・わたしたちが「魔術的芸術」の問題をめぐって、さまざまな専門家たち、しかも高い能力を持つ人に呼びかけようとしたのは、アラゴンやコクトーの討論会などの陳腐さと縁を切りたいと思ったからである。(P88)
・巻末のアンケートの目指すところは、「魔術的芸術」の概念を、決定的に明るい投光機の下に据えることよりも、レヴェルの低下や、すでに脅迫的なものになっている通俗化を抑制させることにある。(P88)
いわば、覚書。
誤字、脱字、解釈などは追々改めるとして、以下に列記したい。
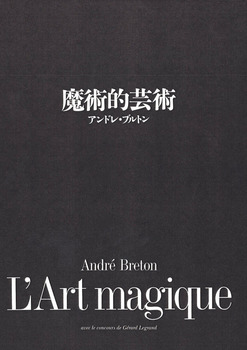
『魔術的芸術』扉
『魔術的芸術』〔普及版〕 アンドレ・ブルトン
監修:巌谷國士
訳:巌谷國士、鈴木雅雄、谷川渥、星野守之
(河出書房新社・2002年6月30日・3,800円)
魔術的芸術の概念
■ノヴァーリスの思想をもとに
・(魔術的芸術は)自ら促進し切望しようとしていた芸術の形態の一つ。(P21)
・パラケルスス「天にあり地にあるもので、人間の中にも存在しないものはない」(P23)
・スェーデンボリ「あらゆる外観、あらゆる物質の形態は、自然の最奥に潜む源泉を見透かせている仮面、包皮であるにすぎない。」(P23)
・上の二つをわがものとし、「われわれは宇宙のあらゆる部分とばかりでなく、未来、過去ともつながりを持っている。とくに重要であり有効であるように思われるこうした強力な関係を確証できるかどうかは、われわれの注意の方向と持続力しだいである。」(P23)
・「世界がわれわれの意思に合致するかどうかどうかは、われわれ自身にかかっているのだ。」(P23)
・「魅力的な娘というものは、人が思う以上に本物の魔法使いである。……すべての精神的な接触は、魔法の杖との接触にている」(P23)
・ノヴァーリスの目からすれば、魔術はたとえ儀式用の道具を失っていても、私たちの日々の生活の中で、その効力のすべてを守り続けているものだろう。(P23)
・ノヴァーリスは、魔術的芸術について、覆いかぶせた言葉で自分の考えを表明している。いわく、「数学は法にしか、つまり法的な自然や法的な芸術にしか関与せず、けっして自然や芸術そのものには係わらない。自然や芸術が魔術的なものになるのは、ただ徳化されるかぎりにおいてである。愛こそが魔術を可能にする原理だ。愛こそが魔術的に作用するのだ」と。(P24)
・「特化」(モラリザシオン)=「精神化」、「徳」、つまり精神的なものに強調が置かれているのは、「フィジック(物質的)なもの」が重くのしかかるつらさを取り除くため。(P24)
・「愛」=精神化され、純化された欲望という意味。「愛する心は、精神のあらゆる要望を満足させる。」(P24)
・これが、充分に進化を遂げた魔術的概念である。(P24)
・魔術は「それ自体として一つの意思にほかならず、その意思にこそあらゆる不思議、あらゆる秘密の大奥儀である。それは存在の欲望の求めに応じ作用する。」(ヤーコプ・ベーメ)(P24)
・上記がノヴァーリスの思想の核心であり、哲学的なものと詩的なものとが合一している地点からこそ、魔術的芸術のまったく異なった二つの側面、二つの様相が、はっきりした形で現れてくるだろう。(ブルトン)(P24)
☆この二つの側面を美術史の枠組みの中でブルトンらが考察するもの。
一方は、必ずしも魔術の直接的表現ではないが、少なくともそれと密接な関係をもっている芸術。→時間と場所に応じて変化しながらも、一つの明確に規定されているある種のコードに従い、現に実践されているような魔術。→人類の揺籃期に形成基盤が見出される。
もう一方は、魔術の組成がすべて消え去ったあとにも生き延びるような芸術であって、故意にであろうとなかろうと、(意識的であると否とを問わず)その後もやはり魔術の手段のいくつかを活用しなおすもの。→これらに見られる魅力によって、目の届く限りの未来を誘い込むもの。
日常の用語方として「魔術的芸術」といった場合、上記の二つのものが混同して、厳格さを欠きながら存在している。(P24~25)
■魔術と宗教の違い
・「魔術」という言葉から――この言葉は、多かれ少なかれ非合理的な性格をもった秘密裏の実践を拠り所にしつつ、自然の諸力を傲然と支配することを目的とするような、人間のさまざまな行為の全体をつつみこんでいる。(P26)
・魔術の特殊な性格の一つ→「あくまでも拘束する」ということ。これが、宗教と根本的に区別される。
・魔術は服従を命じており、違反すれば多くの場合制裁される。(P26)
・「魔術の儀式性は、典礼の各細部に明示されている一つの強い意志の表現であり、その意思は、通常の場合、人間の影響をまぬかれている自然の諸力の支配を求めるものである。」(J・マックスウェル博士)(P26)
・反対に宗教は、「超越的な諸力の贖罪あるいは和解」を目指している。(フレイザー)(P27)
・「供物」は、魔術にも宗教にも共通のもの。(P27)
・「魔術」は抗議、反抗を前提とし、傲慢である。→人間がことをなすことを認める、命令に逆らったものには罰する権利まで与えている。(P27)
・「宗教」は、諦念を前提としている。人間はそこに悲哀と自らに課する苦行以外の何物も期待しない。謙虚である。→というのは、人間をそそのかし自分の不幸についてまで感謝させる。しかも、自分の願いをかなえることを拒否した全能者に対して。(P27)←※ブルトンの宗教嫌いが感じられる。
・上記二つは明らかな違いであるが、「だが、魔術と宗教それぞれの起源を対置しようとするとき(発展過程の比較研究や、時代の流れの解釈の問題を設定するとき、さまざまな困難と論理が対立しあい、例外が多く激しくぶつかり合う。(P27)
・社会学者たちと民族学者たちとは、客観的な配慮を注いでいるだろうが、根本的に相容れない立場の擁護者である以上、自分に有利な論拠ばかりを採集しようとする。
そういう時、隠秘学者たちにも発現の権利がある。――魔術は彼らにとっては死語ではないという権利。しかし、隠秘学者もあらかじめ構想された世界の体系から出発しているわけで、社会学者や民族学者たちとの交流する機会を奪われている。(P28)
・「魔術は世界の調和のもとづくものであり、共感によってたがいに結ばれた種々の力を用いて働く」(ロベール・アマドゥー『隠秘学』)(P28)
■アニミズムの原理
・「人間の中には<原型的存在>の一要素、一植物、一尺度、一理性と照応しないような部分は何一つない」(パラケルスス『魔術』)(P28)
・「魂は、必然的に回帰して、物質と同じだけ個別の魂に分かれる。――物質の中には、魔術から見るとmore magico、個々の体系が他のあらゆる体系の忠実な反映になっていることを妨げるようなことは何もない。(J-A・ロニー)(P28)←この概念は、すでにノヴァーリスのよって共有されていた。
・すでに18世紀にしてアミニズムの原理がヒュームの手に取り上げられている。すなわち「人間性の内には、あらゆる存在が人間と似ているように思い、人間にとって親しい全ての性質、人間が内面で意識するすべての性質を対象に付与しようとする。そんな普遍的な傾向が存在している」(『宗教の博物誌』)(P28)
・「魔術はアニミズムの技術のもっとも原始的で最も重要な部分を構成していり……魔術は、自然の精神化が完遂されていないような場合、どうやらまだ応用される機会がある」(フロイト『トーテムとタブー』)(P29)
・原初の人間たちは、観念の秩序を自然の秩序ととりちがえており、観念を制御できる以上、同じように事物を制御することが可能だと想像していた。ある「共感の法則こそが、自然と人間の関係を、人間に有利なやり方で調整できる。(J-G・フレイザー、タイラー)
種々の観念の連合を類似に基づいて(模倣魔術)、時には空間と時間における隣接のもとづいて(感染魔術)支配すことに他ならない。(P30)
・魔術の根本母体=「マナ」の概念は、魔術と宗教の根株をなす問題(フランスの社会学派もイギリスの民族学者も共通)(P31)
・「煙をたいて雲と雨を呼び起こすという行為に含まれる魔術的な判断は、煙と雲との原初的な区別がまずあって、その両者に結び付けるためにマナに呼び掛ける、ということではなく、思考のより深いところで煙と雲が同一視されている。(レヴィ・ストロース)(P31)
・すべての魔術的行為は、ある合一性の回復に基礎を置いているが、その合一性は失われたものではなく、無意識的なものであるか、行為自体ほど十分に意識されていないものであるかである。(レヴィ・ストロース)(P31)
・「原始人にとって、アニミズムは自然な概念であり、それ自体のうちに正当化の根拠をもっていた。(フロイト)(P32)
・科学界(民族学者、社会学者、宗教史家、精神分析学者)は、魔術を想像的能力の逸脱とは違うとする考え方をひどく不審の目で見ている。そんな精神は、すでに遠い昔にしか居場所がなく、人類の歴史の黎明期がどんなものか検証するためにしか価値がないとしている。(P32)
・しかし、魔術的精神をもつものは、現実の力を意のままに用いる活動としての魔術がかつて存在したばかりではなく、今も存在すると主張する。→これが、最大の不評、最悪の避難、狂信者、ペテン師、として対応された。←「論証的認識」がないため。
では、詩や芸術の世界でそんな認識の言いなりになっていたならとうの昔に想像力は消えていただろう。原典解釈では詩の真価は引き出せない、技法分析では芸術作品の真の効力を何一つ引き出せない。(P32)
☆魔術の伝統に人生をささげている人ならだれでも、詩や芸術に人生をささげている他の人々同様、その伝統の内に認められる永続的な現実と、その伝統の内にあると信じられる種々の力とに合わせて、自己の全内的存在を形作っているのだから、批判的な目で見るような人々に比べて、魔術については常により多くを知るようになるだろう、ということ。(P33)
・「マナ」と同様、「流体」「元素霊」など、合理的分析を拒む概念を拠り所とせざるを得なかった。(P33)
・しかし、詩人たちや芸術家にしても、自分を高揚せしめ、自分の表現の調子にもっとも重大で異論の余地のない効力を与えるような何かに「名前」を付けるとなると同じだけ困難だということ。これは「霊感」という言葉も同じである。(P34)
・論証的認識⇔叙情的認識で、これは言葉の力の再認識に基づいている。
・詩人や芸術家と、魔術的行為の有効性を主張する人々との共通する意見は、「言葉」に与えているところの、高度な、伝達しにくい意味内容の上にある。(P34)
・「ある農夫が毎朝同じ時間に起きて、陽ののぼる前に家からずっと遠いところへ行き、同じ草を毎日1本ずつ摘むことをしたとすれば、彼はこの草を身につけることによって、数多くの奇跡を起こすことが可能であろう」(『高等魔術の教義と儀礼』エリファス・レヴィ)と証言している。これには、どんな本物の詩人も本物の芸術家も異を唱えない。←これは、公認の教育が、気にも留めないような意見である。(P34)
・エリファス・レヴィに共感する詩人=ビクトル・ユゴー、ボードレール、ランボー、ヴィリエド・リラダン、マラルメ。(P35)
☆現在の意識水準(以前と比べ高いとされている)を超えることの原理一切が、自然の秘密についての学という意味での「魔術」の中にあり、それ以外のところにはあり得ない。←そしてここでの「魔術」は超越的な魔術であり、「妖術」とは違う。(P37)
☆「魔術」:ひとつの教義しかなく、見えるものは見えない物の顕現である。感じ取られ目に見える事柄の中には、感覚にはとらわれず目に見えない事柄と正確に比例する形で完全な「言葉」が存在する。(エリファス・レヴィ)←これは、「合理的思考方式」にとっては、まったく無視するしかない称揚し、まつりあげようとするもの。(P37)
・白魔術(降神術)と黒魔術(降魔術)を区別するのは恣意的であって不正確だ。これは魔術的技巧の目的別に考えられたもので、その本性には基づいていない。魔術は一つしかない。秘儀を授かったものは、これを全のためにも悪のためにも利用する。(ルイ・ショショー『魔術とその教義の歴史』)←ブルトンもこの思想に賛同している。(P37)
■ルイ・ショショー『魔術とその教義の歴史』の概要(P37~39)※これは、主に占星術の概念を示している。
・宇宙は一つの球体の中に包み込まれていて、それは有限でも無限であってもいいのだが、一つの星を中心として重力、磁力、熱力などの基本的力によって、めぐりめぐっている。
・それぞれの衛星、惑星上では、さまざまな存在が組織と構造を与えられており、その作用は恒星に起源をもつダイナミズムである。
・存在はそれぞれの種族の可能性に応じて、だが、常に一つの感応力に従って生きている。主動的恒星に由来するこの感応力こそ、存在を化学的にも生物学的にもこの星と一体化させているのだ。
・よって、動物、植物、鉱物といった被造物がどれほど違っていても、摂理に基づいた調和の具現する一連の関係、それぞれの間に連帯を打ち立てている。
・魔術の一般理論は、原則としてたいていは地上界において適用されている部門である。→これは「万物照応」(コレスポンダンス)の理論である。地上界ではどんな存在もひとつずつ構成をもっているが、それぞれの構造に特有の性格は、宇宙のエネルギーのさまざまな組み合わせの結果なのだ。
・これは、銅とクマツヅラの茎とハトの羽は、構造上は違っていても、同じ一つのダイナミズムの拠点であることには変わりがない。←このダイナミズムは、鉱物の場合は潜在的だし、動物の場合は流動的、活動的だし、知性的ではあるが、どれも同じである。
・占星術の教えるところでは、このダイナミズムは「金星」からきている。したがって、金星に感応されたすべてのものは、ある共感、ある相乗作用が働いていて、実践面では、この感応下にある一人の人間は、それに対応する護符を身につけることによって、自分に特有の潜在能力を増大させることができる。(たとえばハトと牡牛、銅とカーネリアン石など)
・ボードレールの言う想像力とは、「まさしく無限なるものと類縁をもち、世界の始まりにあたって、アナロジーを造り出し、隠喩を作り出したものなのだ。(P41)ブルトンはこの言葉とルイ・ショーのものと同じであると言っている。
・ボードレールは、酔って広い意味に理解された宗教というものが、「人間精神の最高度のフィクション」であるとする。(P41)
・ボードレールは、フーリエを馬鹿にしていたが、フーリエはあらゆる人間関係を再検討することで、その関係を「情念引力」とした。
「情念引力」は、魔術の論理に垣間見られる普遍的アナロジーの人間における表出に他ならない。(P41~42)←シュルレアリスムの数々の遊びの中にも見られる。(互いの中に)
・ボス・コーディモ・ゴヤ・ゴーガンなどの絵画の解読にも、この「互いのなかに」の方法を利用すれば、いたずらに「カバラ的」であったり「錬金術的」であったりする解釈よりも危険が少ない。つまり、「偏向主義」ではないやり方の一つだ。(P42~43)←ダリの、パラノイアック・クリティックも同じ。
■近代絵画の魔術性
・J-A・ロニーがボードレールやランボーの詩の中にあると指摘しているような「隠喩における魔術的-生物学的性格」は、詩だけではなく、抽象的傾向をもつ近代絵画にも見られる。――ビクトル・ユゴーのインクの斑紋、ギュスターヴ・モローのエスキスなど。(P43)
・魔術師、芸術家、詩人に共通する「原初の力」は、「万物照応の理論」こそが、その戦術的転化として提供する。
・これは「一つのイメージは寓意でもなく、未知の事柄の象徴でもなく、それ自体の象徴なのだ」(ノヴァーリス)。一つのイメージは、絶対的な想像性を帯びながら、無垢の広がりをもつ共鳴音を、あたかも宇宙の他の部分と結び付けるようにして私たちの内に響かせるような芸術。(P44)
■再び魔術と宗教
・ここでは、魔術がさきか宗教が先かを決定づけることは避けよう。どちらに傾くか客観的な証拠もなければ、決定的な議論もないからである。(P44)
・これらの諸説は「一般的な思考の態度に応じて現れたもので、頑固な先入見によっている」すなわち、魔術は最も直接的なアニミズムにもとづいており、宗教ほど入念な仕上げを前提としない以上、宗教に先行するものでしかあり得ない。
一方、あらかじめ原初の啓示への信仰にとらわれている人々にとっては、魔術の儀式は宗教の儀式が退化したか、それとも神聖をけがされたものでしかあり得ない。という二つの考え方がある。(P44)
・とはいえ、魔術と宗教はともに分かちがたく混ざり合ったものであり、その後の絶え間ない両者の相互干渉を考慮に入れなければならない。(P44)
・「あらゆる時代、あらゆる場所で魔術は行われてきたし、こんにちなお、われわれの間でもそれにふける者がいる。一人の学生が寝る前に教科書を枕の下にしのばせる時、彼はいくばくかの魔力に頼っている。(フランソワ・レグザ『古代エジプトにおける魔術』P44~45)
・こうした中で、芸術における魔術的なものと宗教的なものを区別することはひどく難しいだろう。(P45)
・両者の象徴体系は、事実広汎な共通記号のリストによっている。よって、遠く離れた文明であればある程、その解釈は骨が折れる。「二つの宗教体系が両立できなくなると、弱い方の体系は追放され、魔術の性格をもつに至る。」(J・マックスウェル)(P45)←比較的新しい時代であれば、この区別は難しくないように見えるが、今度は宗教が高位聖職者の統制と手を切った瞬間から(離脱行為のことか?)、新しい混同の要素が見えてくる。(P46)
・俗人の見解とは別に、魔術と宗教は何ら敵対しあうものではないのだ。←この場合の魔術は、奥義を極めた人間が「高等科学」の名をあてがっている魔術のこと。
・つまり、魔術師が非の打ちどころのない特性を備えており、その追求する目的が悪とははんたいのものでありさえすれば、カトリック教会も魔術を断罪することは決してなかった。(ルイ・ショショー)(P46)
・ルイ・ショショーは、黒と白の魔術の区別に異を唱えながらも、この区別は魔術を操る時の動機、あるいは非難すべき動機を説明する場合には適当である。←頂上への道は厳しいが、これに向かうための保証は「心の純粋さ」以外あり得ないだろう。(ブルトンらしい結論付け→愛につながる)(P47)
・魔術のデータ、手段や能力をある程度利用している芸術作品を前にしながら、しかも情報がほとんど与えられていない場合、一見して、これほど透明でも不透明でもいないものをあてがわれたと人々は思う。←つまり、それらのもたらす印象に応じてしか、それらの発散するものが有益か不利益かであったりする度合いに応じてしか、その作品を評価することができなくなる。(P47)
・その上、一つの評価の要因がほかの多くの要因と妥協してしまうし、そのいくつかの要因の言いなりになってしまう。(P47)
■魔術的芸術の範囲(概念の確定)
☆魔術の目的に適合しようと決めていようがいまいが、「芸術作品は魔術そのものを起源としている。」ということを忘れてはなるまい。
「あらゆる芸術は、その発生において魔術的であろう」
ということは「魔術的芸術」という言葉は、同義反復ということになる。
この広い意味を避けるとすれば、「芸術を生んだ魔術を何らかの形で自分から生みなおすような芸術だけを、特に「魔術的芸術」として取り上げることだろう。(P49)
・芸術作品は、かつて世界の創造を司ったものと同じ性質のダイナミズムが物質の局面の上に客体化されたものだとする発想が、グノーシス派の人々の間で脚光を浴びている。(P49)
・「肖像画が生きている人間の顔に劣るのと同様に、宇宙は生きているアエオン(永遠なるものの意)に劣っている。とすれば、肖像画を描く動機は一体何か?」と、ヴァレンティヌウスは問うている。←「それは、顔の尊厳である。顔がその名を通して名誉を得るようにとモデルが画家にその顔を提供したのである。つまり、形態がそれ自体見出されていたわけではなく、「名」が作品の原型に欠けていたものを満たしたのである。」(P49)
・聖なる恐怖=「神の名において」造られた自作を前にしたとき(言いかえれば、より高位にある未知の原理を前にしたとき)、芸術家を捉えるのはあの畏怖の念である。←アルニムも同じ発想をしている。(P50)
・アルニムは「未だ創造されていない何者かに対する発明家の信仰(そのために深遠に身を投じ、魂のすべてを混沌にゆだねる信仰)は、優れて神聖なものである。
だからこそ、この信仰は傷つきやすいし、いやしがたい。この恐怖こそが畏怖の念に等しいと。そしてこの宇宙は、われわれの企てに屈することなく、われわれを利用して実験や気晴らしにふけっている。(P50)←プリニウスはアフリカの蜃気楼を、すでにこうした自然の気晴らしのせいだとしている。
☆ロマン派の時代から、今日に至るまで、われわれ自身の力を超える何者かの力にもてあそばれていたり動かされていたりとする感覚は、詩の中でも芸術の中でも、幅を利かすことをやめない。(P50)←「私が考えるというのは間違いです。誰かが私を考えている」(ランボー)
プリニウスは絵画の起源について、「すべてのギリシャ人の言うところでは、絵画は人の影を線でなぞることから生まれた」としている。また、粘土を加工して像を作る方法を発見した最初の人は、娘が男に惚れて、男と別れる時その男の輪郭を線でなぞり、粘土でかたどったことによる」(P53)
・これは、土や鉱物といった絵画を生み出す物質の支えを見失うことなしに、魔術的な角度から考察されている。(P53)
・またプリニウスは、絵画のだまし絵的効果も評価と同時に限界をも示している(鳥とブドウの話)(P53)
・芸術の要求がどんな模倣も受け入れない時、その成功は「偶然」の働き掛けによるものではないか?←犬の涎を描けなかったものが、スポンジを投げつけた時偶然にもそれが再現された。など。(P53)
☆、このように、どんな芸術も魔術と密接な関係を保っていることがよく分かる。しかし、このように魔術に依存しているにもかかわらず、長いこと思考を従属してきた「合理主義」の潮流のおかげで、数世紀にわたって抑圧されてきたことも事実である。(P53)←芸術に豊かさが失われている。
・19世紀を通じて公認のサロンの繁栄とブルジョワ階級の悦楽をもたらした山のような絵画作品は、特にこのような豊かさに欠ける。(P54)
・生活の中でも自然の中でも、月並み調の事物の存在がある。この俗悪で凡庸な存在は、偉大な芸術家たちは忌み嫌っている。とボードレールは言う。(P54)
・またボードレールは次のようにも言っている。
「もしも美を表現することをまかされた人間たちが、教授、審査員諸氏のルールに従うならば、美それ自身が地上から消えてしまうだろう。なぜならば、あらゆる類型、あらゆる感覚が単調で没個性な倦怠や虚無のように果てしもない巨大な統一体の中で混じりあってしまうだろうから」(P54)
・「古典芸術」「バロック芸術」「宗教芸術」にたいして、「魔術的芸術」は揺れの大きいものであり、前記の諸概念と部分的に重なってしまうという事実からもそういえる。(P55)
・美が本当の意味で美しいと感じらとられるためには、私たちの感受性のいくつかのゾーンがそれによって昂り、さらにその高揚を超えて、人間の条件につきものの醜さの感覚から出たこの壁の裂け目を作るのにふさわしい、一連の波動が起こるのでなければならない。←これは、政令によって交付することはできないだろう。(P55)
・ブルトンを含むある種の精神の持ち主には、ある程度魔術的でない美を思い描くことが難しい。これは、美に付け加えられた受動的な、もっぱら反射的な属性であることには変わりない。もはや、美ではない「魔術的なもの」をこそ熱望し、美に対する魔術的なものの優位性を認めることが必要だろう。(P55)
・この行き方は、必然的にアニミズムの段階における歩みを再現することになるだろう。(P55)→つまり、もろもろの存在を統合し、配列し、活性化させている神聖な力を人間に従属させるようなところから始まり、原始的なアナロジーが、初歩的ではない観測を生みだしたその瞬間から、「象徴思考」に達していく歩み方をである。(P56~58)
■古代の魔術的芸術(魔術的トーテミズム)
・古代が残していった作品には、魔術の実践を立証し、しかもある程度それを再構成する助けになるものが数多くある。
しかし、わずかな例外を除いて私たちに働き掛けてきたものは、それらを方向付けた「魔術」ではなく、むしろそれから発する「美」によってである。「美」を副次的にしか追及していない作品の場合でさえそれは同じである。→つまり、そこに暗示されている儀式が長いことヴェールに覆われていたため、別の性質をもった同じ角度の(美的)評価のもとにあったわけだ。←つまり、誤解されて評価されていたということ。(P58)
・これらは、「魔術的芸術」であったにしたところ、肝心かなめの情報量が少なく、それが特別の手ごたえを感じるところまでにはいかないのだ。(P58)
・これと比べて、魔術的荷重を少ししか失っていないものに、各地に散らばって生きている民族集団の活動の所産である。(P58~60)←野性人と呼ぶべきだろう。
・これらは不毛な地域へ追いやられ、狩猟、漁労、牧畜、初歩的な農耕といった資源の少なさから比べると、芸術の旺盛さは心を揺さぶられるほどに豊である。(P60)
・民族学者は、これらの芸術はトーテミズムの内に見られることも一致している。←何よりも魔術的である。(魔術的トーテミズム)(P60)
・ロテュス・ド・パイニは、魔術というただ一つのものだけが、被造物人間に感受することと、思考することと、意志することの三能力を授けてくれたのだと感謝している。(P60)
・そして「大いなるトーテムが古い歴史のすべてを支配していることを知らなければならない」とし、トーテム思想のアボリジニ、ニューギニア、インディアンの芸術は特別のものと位置づけられる。(P61)
■ヘルメス思想
・文明の進歩も、技術の発達も、人間の心のうちから世界の謎を解くという希望を達成することはできなかった。「ひと目ではひどく錯綜しているようにみえながらも、少しずつ解きほぐしてゆくことのできる道筋←ヘルメス思想のさまざまな諸部門。(P61)
・ルネ・ゲノンによれば、「魔術」は下位にあるのだが、諸部門の先導者の役割を果たしている。なぜならば、魔術は幼少期のおとぎ話の生き生きとした登場人物たちを作り出すからだ。(P61)
・魔術の記号のリストは、ヘルメスの諸部門のそれと根本的に同じである。よって、占星術、カバラ、タロット、卜占術、加護祈祷、いくらか保留付きの錬金術を通る図像学的探索を続けていけるはずである。←美しいという角度からはもちろん、これらの作品の価値は実にさまざまである。(素朴なもの、単純なものから最高度の技量に満ちたもの)(P63)
・これら、デューラーの版画も行商文学の木版画との間の尺度の違いはない。両者が私たちに及ぼす魅力は、発揮されている力量とは関係なく、その魅力は突飛な性格に存しており、面喰わせる力の大小に応じている。(P63)
・「美は常に珍奇なもの」(ボードレール)「個性というものを構成し、意義づけ、それなくしては美など存在しなくなるこの珍奇なるものの服用量は、芸術において、料理における風味、あるいは調味料の役目を果たす」(P63)
・幾世紀ものあいだ公認の評価を享受していたかなりの数の芸術作品が、この調味料を根本に欠いているという理由から、価値が低くなっているものもあれば、逆に長いこと好奇心にとどまっていた他の芸術作品が、第一級資料になることもある。(P64)
・そうした作品は、大体が顕在的にであれ、潜在的にであれ、非合理な内容を呈しているものか、かなりの曖昧さを示すものである。(P64)
・ロベール・ルベルは、「ヴァン・エイクからモスタトールにいたるフランドル絵画と、マンテーニャからピエロ・ディ・コージモに至るイタリア絵画は、変身の途方もないリストである」と。(P64)
・同時代人であるボスとダヴィンチ。二重画像はある世界の基礎、正真の造形カバラのカギとなるものだ。←両者はともに統一性に取りつかれていた。ボスは道徳的なものであることを求め、ダヴィンチは、自然なものであると考える。『聖アントニウスの誘惑』など具体例が続く。(P65~68)
・ルネサンスの強要する合理主義的人間主義は、芸術において物理的な視覚に支配権を与え、一切を感覚的経験に関連付けることになる。反動として起こるマニエリスムも、その拘束を狭い範囲で振り払うことしかできない。
それに歴史は、流れに逆らって仕事をする芸術家たちの寄与をできるだけ長い間考慮に入れることを避けている。(P66)
・コージモ、デューラー、グリュネヴァルト、アルトイドルファーといった画家たちの作品が、しばしば謎めいたやり方であるにしても、一つの要請にこたえていた。(P68)
・より身近にあるものではあっても、それらの作品は不信、あるいは忘却に見舞われていたために近づきにくいことに変わりはなかった。そうした作品の典型として、アルチンボルト、カロン、デジデーリオのものをあげよう。確固たる外観を持ちながらも、気まぐれや偏帰志向の産物として見られなかったが、近代の視覚のこうむってきたある種の角度変更を出発点として、別の解釈にゆだねられているように思われる。(P70)
・「謎を呈する」絵画のうち、「歪曲した円錐鏡像」の原理に基づくホルバインの「天使たち」など、まるで媚薬のように働き掛けてくる。(P70)
■プレ・ロマン派
・プレ・ロマン派は、フランス革命、アメリカ独立戦争といった精神的動揺が深い社会的危機に呼応していた時代の表現として、芸術における諸価値の復権を目指す。(P70)
・そのために、これまでの「光明」の三世紀と縁を切り、中世世界のいくつかの強迫観念を生き返らそうとする。(P70)
・よって、19世紀はこの方向に沿って、ユゴーやロマン派の主だった顕楊者たちの造形作品を通して、立場を明らかにし始める。(P70)←実証主義が勝利をおさめた結果、芸術において、見せかけの世界にそむこうとする意志が抑制されるに至る。(P70)
・メリヨンの場合は、誰よりも厳格だったレアリスムの枠組みを破砕せしめ、誰も望まなくなった劇的な別次元の意味を復元するためには、「錯乱」が侵入しなければならなかった。(P70)
・19世紀後半になると、「失われた諸力」を回復しようとする欲求はすでに侵食していたので、詩においても芸術においても、「視覚には、幻視や透視と比べて二義的な位置を与えられた。」←エリファス・レヴィの秘教思想と必然的に再び接するようになる。(P70)
・だからって、「客観的現実性」を自然と競おうとする芸術の信奉者――印象派など――は、武装解除した訳ではない。(P72)
・印象派は光に第一等の役割を与え、ごく小さな気まぐれにさえ頼って光を賛美した。これが、ある一時期、光の新たな正当化を行い、主題の若返りを図った。(P72)
・しかし、印象派と同じ時期に、ギュスターヴ・モローが燦然と輝いてきた。(P72)
・ロマンティシズムの画家C・Dフリードヒの厳命。「おまえの肉体の目を閉じよ、まず精神の目でタブローを見るために。ついで、おまえが、おまえの夜の中に見たものを陽のもとに上らせよ、その作用が、外部から内部へと逆方向に他の存在たちの上まで及ぶように」(P72)
・ギュスターヴ・モローの「神話的象徴主義」から、ゴーガンの「総合的象徴主義」、ルドンの「夢幻的象徴主義」まで、この移行はマラルメやユイスマンスによって保障されることになる。(P73)
・こうした二つの傾向(視覚に頼った印象派――覚醒の時間を捉えて見せた方向と、心の目に頼ったモローなど)は、20世紀にいたって、いよいよ鮮明になり、今日では熾烈極まりない様相を呈している。(P73)
・覚醒の時間に捉えてみた方は(印象派など)その後フランスでは後退し始めている。フォービズムは、ゴーガンやゴッホの教えをその精神において裏切り、視覚神経のみによる知覚からだけ興奮を導こうとする。キュビズムは、純粋な技術上の約束事としてヘルメス的秘儀といって、人間の顔でしかないもを描く。(P73)
■後期印象派とルソー(無意識)
・スーラ以降の後期印象派と、ポン・タヴェン派(フィリジェは例外で)が妥協の道に入り、一方は初歩的な写実主義へと、他方は戒律の厳しい精神主義へと移行しながら、急速な衰退を見せている。(P73)
・それに対して、ルソーが観衆の嘲笑を迎えられながらも、ジャリ、ゴーガン、ピカソ、アポリネール等に興奮を呼び起こしたのは徴候的である。(P73)
・このルソーに対する興味も、はじめは見下したふざけたものだったが、のちには驚嘆へと変貌していく。ルソーをめぐって、はじめて「魔術的レアリズム」を語ることができる。(P72~74)
・私たちの中でも、審美的、合理主義的な先入見のおかげで、それを評価できない状態になっているものと、いないものとの間で成り立つコミュニケーションは、実に突発的で魅惑的なものであり、明らかに大きな効力を発揮し、既知の手段をことごとく挫いてしまうものである以上、「魔術的因果関係」を持ち込むのは当然である。(P74)
・しかし、このルソーの問題が把握されるのは、無意識なるものにあたらしい現実性を授ける見方のおかげでしかなく、その現実性こそが、無意識に対して王者の分け前を与えるのだ。(P75)←この見方は、19世紀からあったものの、20世紀になって初めて照射された。
・「意識とは明確な活動に隠されている潜在能力の孵化であり、転化であり、一つの源泉を有する噴出のこと。無意識は、心理的な、形而上的な、神秘的な性格をまとう。」(P76)
・魅力を発揮できる作品とは、たとえ合理的には正当化できないものでも、意図的にであれ、無意図的にであれ、精神の無意識的領域に根株を下したものに他ならない。(P76)
・ルソーの単純さは、一般には規範からはずれていて、さまざまな禁忌から彼を守っていたが、これをランボーやロートレアモンが全面的な反抗と引き換えに初めて希求しえたものだった。←これは、ゴーガンがもっと素朴に、ポリネシア人のところまで探しに行ったものである。(P76)
■現代作家たち
・フランスでは、ゴーガンのメッセージも、特にフォービズムが視覚神経の昂揚の可能性以外のものをそこから受け止めようとしなくなって以来、台無しになっていたのだが、外国ではムンクがこの教えから全く違う一つの解決策を見出す。(P77)
・ゴッホも、ゴーガンも、人類の運命に対する大きな問いかけの精神が宿っているが、ムンクも、人生の情景を示す悲劇的で狂おしいもの全ての中に私たちを突き落とす。(P77)
・ムンクは、「造形的探索をめぐる内面の動揺を計測するような」ところがある。(P77)
・同じ見方からすると、無限の衝動に基づくものあっても、悲劇性の強度の点でムンクに勝るとも劣らないのがアルフレート・クビーンの作品である。(P77)
・注目するのは、キュビズムの誕生を左右したもろもろの意図、外的対象のすべての側面を同時に伝えようとするキュビズムの意思が、それまで理解されていたイリュージオニスム(錯覚表現)の基礎をなす視覚的レアリズムに対して、一挙に背を向けてしまったという観察である。(P78)
・ピカソの「クラリネットをもつ男」や、ブラックの「ギター弾き」のようなタイプのものは、特定の音楽奏者を画面から消し去り、性質は不明確でも、構造の見分けがつく一つの存在を、私たちの目に生き生きと描き出す。その存在は、自らまとう奇妙な様相によって、よかれあしかれ、私たちをその力に従わせる。←そんなキュビズムの画家たちがどんなに合理的にやろうとも、観者のほとんどが得られた結果しか考えないのが当然で、多かれ少なかれ、同意の上で「鏡の向こう側」にいる自分に気がつくと子になる。(P78)
・ダリは、このピカソの作品を演説するものが誰一人何を描いているかが分かっていないということを思い出して大喜びするが、ダリは、観者の精神の中で、ある本物の革命が行われていたという事実を見ていない。ダリが標榜し続けている写実的など、とうの昔に無効だという事実も見ていない。(P78)
・絵の主題の解明など無視してよい、とまで言わなくても、少なくても副次的なものにすぎないと考えさせることは、言葉の広い意味で、芸術家と観衆との間に生まれる交流は、確かに魔術的であるとみなさなければならない。(P79)
・第一次大戦の前夜に造形芸術の分野で、どんな興奮状態が出現したかは周知のとおりである。(P80)
・1910~1914にかけて、外観だけの世界と手を切って、その代わり何かを打ち立てようとする欲望が前例のない激しさであふれ出ている。文化の新しい欲求と、その要求の感覚的世界におよぶひそやかな反響とに呼応した世界。←その原理は、長い間「模倣」への関心の犠牲になっていたため、「写実主義的」拘束によって、遠ざかれていた。(P80)
・その時代の英雄がアポリネールである。←彼の並はずれた好奇心を満たすことを目的とし、その結果、必然的に彼の深い不安に順応してゆく。この不安があの好奇心と同じ理由から、魔術的な種類のものと確認できる。(P80)
・アポリネールらによって、観衆は、「習慣」に水を差され(現実という幻想から汲まれるすべての安息の喜びを奪われた)、激しく抵抗する。(P80)←観衆には、この幻想が網膜に対するごく特殊な教育の所産であることに認める用意がない。
・「もしも、野性人がわれわれの表現規範に従う一枚の絵を見たとしても、そこに我々の見ているものは何一つ見いだせない。という反論を差し向けられても、せいぜい自分たちの優越性を見出すくらいだ。(P80)
・キュビズムと未来派は、想像しいし示威運動で境界付近に生まれた少数の個人の作品の意図に含まれる、はるかに壊乱的部分を観衆の目から隠してしまう。(P81)
・それらが、一方ではキリコ、シャガール、デュシャンであり、他方ではカンディンスキー、モンドリアンである。(P81)
・キリコは、ソクラテスやニーチェの思想に糧を得ていた彼は、事物の秘密の生命に発するものではないものは、どんな要請も排斥してしまう。(P82)
・物体の外的様相が尊重されているとしても、その物体はそれ自体としてではなく、それを始動させる信号としての関連において愛でられる。←この信号は、運命の感覚、ないし力をもった一本の交線のひかれる可能性が予想される。(P82)
・問題は、すでに形象化された諸要素を一目で識別するささやかの悦びでもないし、「通人」気取りの制作方式を賞味することでもなく、外界の諸相から謎を生じさせるものだけを引き出そうとする絵画は、卜占術と本来の芸術とを一体化させる方向へ向かう。(P83)
・ラウール・アリエの考えるように、「常軌を逸したもの、予想外のもの、不思議なもの、つまり一言でいえば驚きを呼び起こすものだけが、人間の意図に自問を強いることができるのだ。」(P83)
・キリコが、独占的な要請と誘因とを身に受けたこの高位の因果律こそ、魔術的因果律と境を接するものなのである。(P84)
・シャガールは、キリコと同じころ、「感傷的というよりも、むしろ夢幻的な活力を横溢させながら、無尽蔵であると仮定しうる無意識の資源を誇示していた。」(P84)
・シャガールのエロティシズムと、フォルムの透き通る柔軟さは、表現主義とキュビズムに隣り合うものだが、いささかおとしめられている民間魔術の概念をみずみずしくよみがえらすことのできた美質の、典型的な一例である。(P84)
・カンディンスキーは、さらに深い闇な中へ降りていく。「抽象的」という誤解がこれほど行き渡ったことがない。(P84)
・カンディンスキーの壮麗で野蛮な和音は、厳格なあるいは錯乱的な描写と同じく、美的活動のコースをひとめぐりして戻っている。(P85)
・キリコとカンディンスキーを拠り所として、20世紀半ばの「物の数に入る」ほとんどの絵画は発展してきたといってよいだろう。(P86)
・彼ら二人の隠然たる存在は、本物の魔術的な芸術になりすまそうと企てている、紛れものの群れの中にもしばしば感じ取られる。←キリコは、ネオ・アカデミズムに落ちてしまい、夢幻絵画や安物のシュルレアリスムにの先駆になったこと。カンディンスキーは、若い抽象画家によって、悪用されている。(P86)
・実際、そうした画家たちの尊大ぶりと、幾何学の規格大量生産とが、極めて高貴な精神を身につけているはずがない。(P86)
・キリコと、カンディンスキーという天秤の竿になっているのがデュシャンである。デュシャンは、雰囲気の撹乱という方向で作用してきた。(P87)
・そうした作品は、物質的にも精神的にも近づきがたいものであり、反芸術である。(反詩的ではない)(P87)魔術とは「アンチ・リアリティ!」である。(P87)
■まとめ
・今日の批評界は商業界と同じく、思想とも、人生の真の「内的」問題とも何らか変わらない示威行為の数々を大げさにもてはやしている。(P88)
・19世紀を通じて、芸術家と詩人たち、詩人たちと哲学者たち確立されたかに見える合意も、徐々に崩れ落ち、豊かな協議を大きく犠牲にしている。(P88)
・「美」はこれこれの顔をもつようにと催促され、結局は最大多数の理想にあった顔、つまり凡庸な顔をさらすことになる。←真価の混乱、反射行動の抑圧、反詩的な教育がこれほどまで進行したためしはかつてない。(P88)
・わたしたちが「魔術的芸術」の問題をめぐって、さまざまな専門家たち、しかも高い能力を持つ人に呼びかけようとしたのは、アラゴンやコクトーの討論会などの陳腐さと縁を切りたいと思ったからである。(P88)
・巻末のアンケートの目指すところは、「魔術的芸術」の概念を、決定的に明るい投光機の下に据えることよりも、レヴェルの低下や、すでに脅迫的なものになっている通俗化を抑制させることにある。(P88)
2013-08-12 13:58
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)







コメント 0